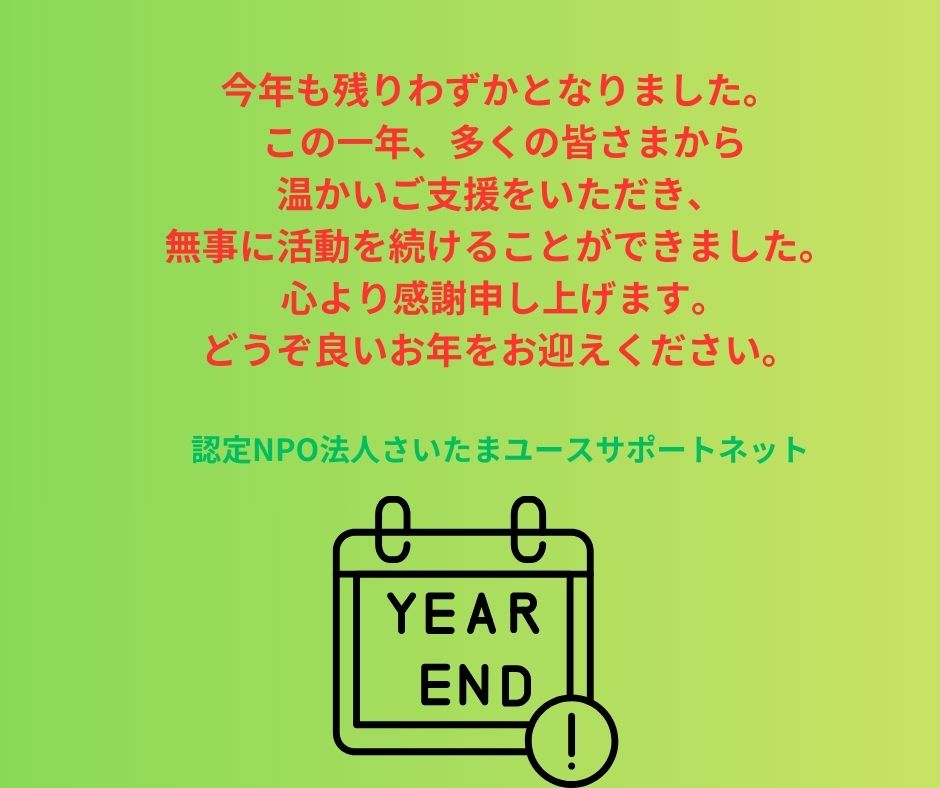書評:『貧困・孤立からコモンズへ―子どもの未来を考える』_ローカル・コモンズをひろげていくために
阿比留 久美(早稲田大学)
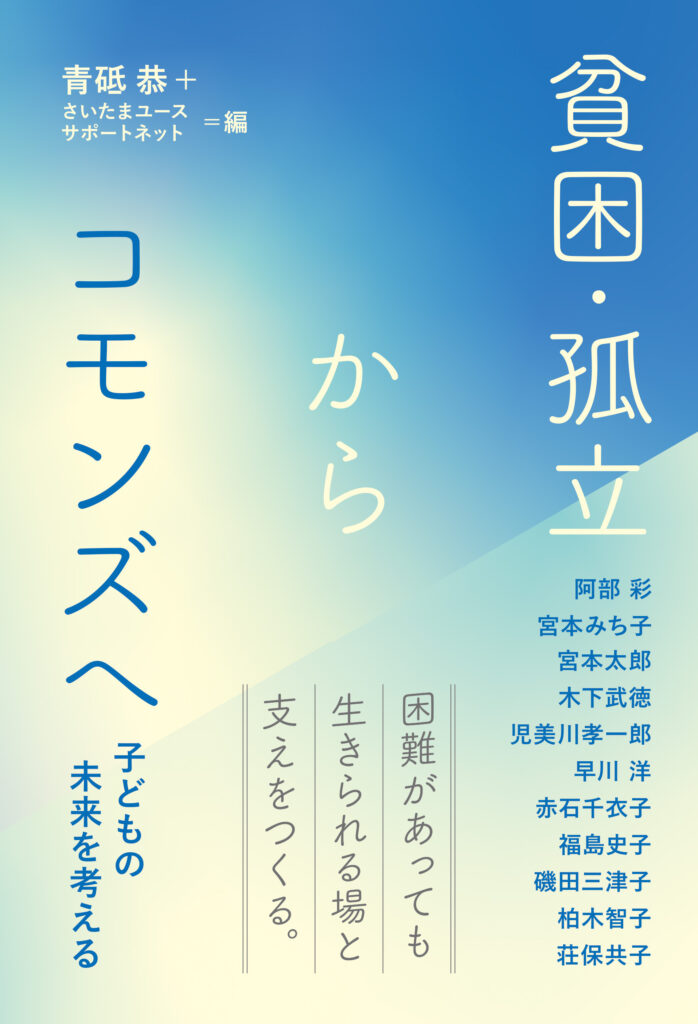
現代社会では、義務教育時から家庭的にも学力的にも困難をかかえる子どもが特定の場に囲い込まれることで不可視化され、かれらの困窮と不利が子ども期から大人期に至るまで蓄積されていってしまうシステムとなっている。ユースサポートネットの青砥恭氏はそのような状況に対し、市場原理にゆだねてはならない福祉・教育・医療・環境などは「非市場」とし、「市場原理主義(新自由主義)によって貧困と格差、分断が覆う社会を、連帯と持続可能なものにつくりなおすために、地域の住民や社会資源が主体となって、地域社会に基盤をおいた「ローカル・コモンズ」のモデルをつくること」を目標としている。
第一部では、そんな「ローカル・コモンズ」のモデルをつくるための視点を提示している。子どもの貧困の第一人者である阿部彩氏は子どもの貧困の実態を解くと同時に、貧困家庭の子どもを対象とした施策のみでなく貧困家庭の家計そのものを支えるよう提言している。宮本みち子氏は、立ち上げから自身が深くかかわってきた若者支援政策の課題を指摘しつつ、こども基本法時代の支援として、子どもの意見表明権と意思決定支援、子ども政策と若者政策の接合を提言している。宮本太郎氏は、現行の全世代型社会保障と少子化対策の課題を指摘しながら全世代型セーフティネットのあり方のひとつとしてベーシックインカムを紹介している。木下武徳氏は、社会福祉や貧困対策が市場化に向かないことを指摘し、NPOの連携を進め、「協働モデル」や「共同生産」(コ・プロダクション)の可能性を指摘している。児美川孝一郎氏は、新自由主義的な学校改革がもたらしたものをふりかえりつつ、キャリア教育が実質的には「勝ち組のススメ」と「転落への脅し」として機能してしまっている現状に対し、あらためて教育に何ができるかを考える必要性を提起している。
このように、子ども・若者が育つ基盤が現在どうなっているかを理論的に考察したうえで、第二部では「いのちを支える場と支援」がどうなっているかを見ている。そこでは、児童心理治療施設(早川洋氏)、ひとり親家庭(赤石千衣子氏)、スクールソーシャルワーク(福島史子氏)、外国につながりのある子ども(磯田三津子氏)、学習支援(柏木智子氏)の現状と課題、そして提言がなされている。
厳しい状況におかれている子ども・若者の状況に対し、荘保共子氏と青砥氏が提起する「ど真ん中にあるべきは、ひとりひとりの子どもの命と権利」という問題提起は、こども基本法・こども家庭庁が動き出している現在切実に応えられるべき課題である。
子ども・若者の貧困の打開策として、青砥はローカル・コモンズに可能性を見いだしている。そして自身が埼玉県で実施してきたローカル・コモンズの実行体制を堀崎プロジェクトとして紹介している。
ネグリとハートは、「地球の富や社会的富といった、私たちが分かち合い、その使用を共同で管理運営するもの」を〈共〉と表現する。そして、〈共〉を様々な形態に生み出し、使用する、広く異種混交的な主体性が協働する回路として社会を想定する(アントニオ・ネグリ&マイケル・ハート『アセンブリ――新たな民主主義の編成』岩波書店、2022年)。青砥氏が想定するローカル・コモンズは、ネグリとハートのいう〈共〉が自律的に用いられる社会と共通するものが大きそうだ。
では、ローカル・コモンズという思索的な社会イメージはどのように具体化しうるのか。さいたまユースサポートネットには、堀崎プロジェクトがどのように有機的なものとして展開しているのか、その具体的動態を共有し、ローカル・コモンズが各地へと広がっていく動きへとつなげていくための知恵を共有していってくれることを期待したい。それはローカル・コモンズにおけるローカルな知が、より広域に広がっていくことと不可分であり、それによって、開かれた〈共〉が拡大していくのではないかと私は考える。
他の書評については、下記URLからご覧下さい。
▶貧困・虐待・ヤングケアラーそんなの昔は当たり前たった。では、昔の当たり前が今はなぜ問題なのか?_松田考
▶『貧困・孤立からコモンズへー子どもの未来を考える』初学者をぜひ手に取ってほしいー
貧困を孤立をめぐる子ども・若者支援の現在地をとらえる良書_萩原健次郎
▶書評:『貧困・孤立からコモンズへ―子どもの未来を考える』_ローカル・コモンズをひろげていくために_阿比留久美
▶書評:青砥恭+さいたまユースサポートネット編『貧困・孤立からコモンズへ 子どもの未来を考える』(太郎次郎社エディタス、2024年)山田哲也(一橋大学教授)_山田哲也