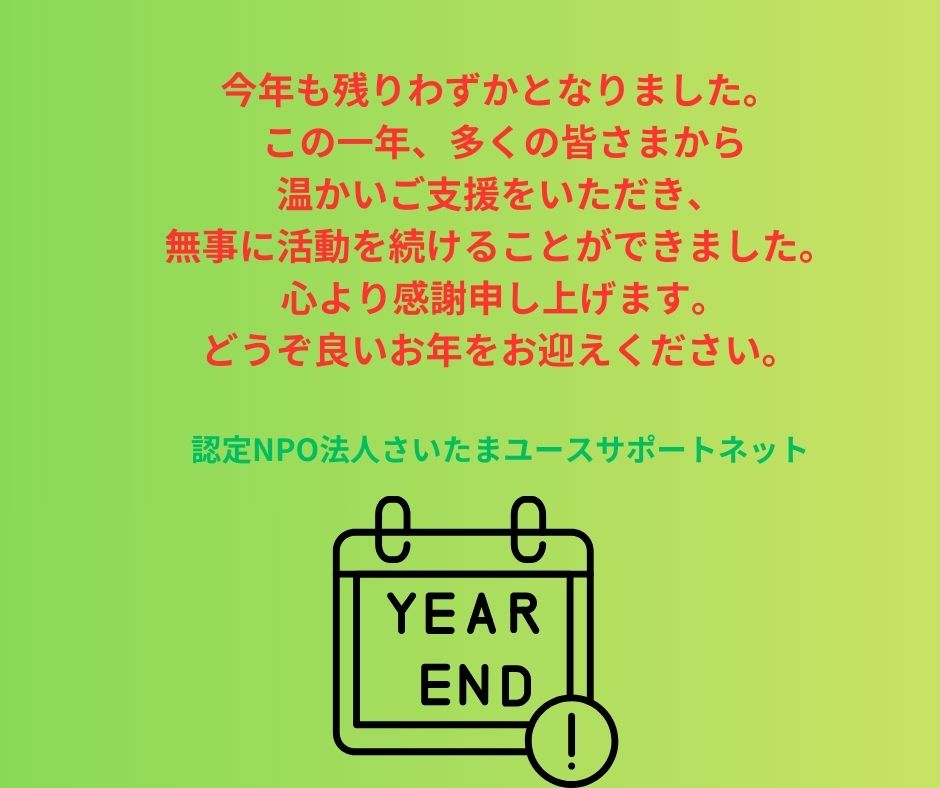2024年度第3回 堀崎プロジェクト運営協議会のご報告
3月18日に、さいたまユースの見沼区堀崎町の本部拠点におけるプラットフォームの活動について運営協議会を開催しました。行政、住民組織、近隣の小中高校、大学までの学校、ロータリークラブの企業経営者、福祉関係の民間支援団体の代表が参加しています。さいたまユースの活動のビジョン・ミッションでもある「地域づくり」の中心的な活動でもあります。
2024年度第3回 堀崎プロジェクト運営協議会(まとめ)
(代表)年度末のお忙しい時期、令和6年度第3回堀崎プロジェクト運営協議会にご出席いただきありがとうございました。協議会は以下のような内容で開催されましたので、ご報告いたします。今回の「堀崎プロジェクト運営協議会」は先週、研究者が参加した、「評価委員会」をうけて開催されます。
1 開催概要
2025年3月18日(火)14時00分〜16時00分
於認定特定非営利活動法人さいたまユースサポートネット堀崎事務所スタジオ
2 議事
(1)報告「分断と孤立化を超えてローカル・コモンズをめざす地域のプラットフォーム形成に向けて」について
(2)意見交換:堀崎プロジェクトで見えてきた課題とケースの検討について
3 発言要旨
(1)代表理事(青砥恭)
➡ 運営協議会の目的
〇 私たち、さいたまユースは、2011年7月の団体設立から、さいたま市を拠点に、「地域」に根ざした活動を目指してきました。虐待、ヤングケアラー、障がい(発達・知的)、学校での暴力・いじめ・不登校(長欠)・高校中退、自死願望など、生きずらさを抱える子ども・若者、家族に寄り添いながら、地域から支える仕組みづくりをつくることを目標に、居場所づくり、学習支援、就労支援から地域づくりと、活動を続けてきました。
この活動には、地域住民・組織、自治体、学校、大学、企業の参加をいただき、持続的・包括的な組織に発展させる、「ローカル・コモンズ」形成を目標にしてきました。「堀崎プロジェクト運営協議会」はその関係者が参加する話し合いの場、さらに運営母体をめざし始まりました。
今回の運営協議会では、子どもたち(小・中・高校生)の「いじめ・暴力行為・不登校(長期欠席)・自殺」、虐待対応件数、教員の精神疾患(1980年代と比較し、10倍化)等が過去最多になっている状況を踏まえ、すべてを学校任せ、家庭の責任にするのではなく、地域社会ができることは何か、話し合いましょう。
◯地域から、子どもや家族の貧困、孤立が見えなくなっています。「孤立する子どもと家族をどう支えるか」が中心的なテーマであり、そのためには行政、地域社会、NPO等の民間団体の連携が不可欠です。
◯また、「分断と孤立化を超えてローカル・コモンズを目指す地域のプラットフォーム形成」というキーワードは、地域の方々は、地域で暮らす多様な人々が地域社会で暮らす人々を互いに支え合う地域社会の構築を目指しています。
◯いじめ、不登校、自殺、虐待の発生・対応件数がいずれも過去最多となっており、子どもを支えている教員の精神疾患の発生件数も、「1980年代に教員の精神疾患での休職者は600人程度だったが、現在はその10倍にも及ぶ」との国のデータもあることが報告され、教育現場の深刻な現状が示されました。
◯そのような中で、学校だけで課題を抱える子どもたちを支えるのではなく、地域が主体となって連携(ローカル・コモンズの形成)し、支援の輪を広げていく必要があるとの認識が示されました。
(2)就労支援事業統括責任者
◯就労支援に関する活動報告では、支援対象の多くが不登校や引きこもりを経験し、対人関係への不安、虐待やいじめのトラウマ、発達障害など複合的な課題を抱えていることが共有されました。
◯支援が必要な若者との個別相談を起点に、信頼関係を構築し、段階的に社会につながる体験活動や職場体験を実施しています。
◯たとえば、隣接する堀崎自治会館での清掃活動、地域畑での作業、市民イベントへの参加などが行われており、社会性や自己肯定感の回復を図っています。
◯また、支援が必要な若者が地域企業と連携しながら地域の自治会のホームページの制作、ロゴデザイン・システム検証等を行うことで、実践的なスキルを習得しながら自己効力感を育んでいます。
◯さらに、埼玉県内の公立定時制高校、通信制高校と連携し、就労体験・講話・校内カフェ設置などの支援が展開されています。
(3)運営協議会への出席者(委員)の主な発言
◯地域企業からは、若者の成長を支えるために音楽や職場体験の提供を行っているとの報告がありました。
◯「(土曜日の子どもたちの合唱グループの活動)音楽を通じて小さな努力が拍手喝采に変わる」という成功体験は、若者の自己肯定感の醸成に寄与しています。
◯企業見学や就職支援を通じて、若者が実社会に出るための準備を行っている実践例も紹介されました。
◯精神障害を抱える若者の支援に関して、「精神障害という言葉自体が壁になっており、家族も本人もなかなか相談に踏み出せない現状がある」ことも障碍者支援をしている委員から共有されました。
◯「精神疾患は誰もがなりうるが、回復できる病気である」との認識を広めることが大切であり、精神科医療に頼る前に相談できる場所(街中保健室など)を地域に増やす必要があると話された。
◯また、ある家庭では、進学費用の相談を契機に訪問したさいたまユースのスタッフが、実際には母親の介護を担うヤングケアラーである息子の存在に初めて気づいたというケースが報告されました。
◯「ふだんから雨戸が閉まりっぱなしで、民生委員も訪問できなかった」という状況からも、支援が届きにくい家庭の実態と発見の難しさが浮き彫りになりました。
◯こうした家庭にアプローチし、支援へとつなげるには、学校区などの小さな単位での協議会や連携が重要だという意見が出されました。
◯さらに、外国ルーツの子どもたちに関する課題も取り上げられました。日本語指導や進学支援、居場所の提供に対するニーズが高まり、見沼区や北区など、複数の地域から子どもたちが通ってきていました。「居場所はあるが部屋や送迎が足りない」といった運営面での課題も共有されました。
◯また、教室に馴染めず孤立している子や、誰にも把握されていない不就学の子どもたちがいること、定時制高校でも1年生の段階で学ぶ意欲を失い、そのまま学校に来なくなる外国籍の子どもたちがいる実情も明らかとなりました。
◯「学校に来ない子をどう地域につなげていくか」が大きなテーマとして浮かび上がりました。
◯一方、行政の委員からは、保護者が支援に関心を持ちにくい現状が課題であり、「市や福祉課と連携は取れていても、家庭に踏み込むのが難しい」という声が上がりました。
◯学校内ではスクールカウンセラーやSSW(スクールソーシャルワーカー)を中心に、教職員と情報共有しながら子どもたちを見守っているが、「それだけでは足りない」「外の世界を知ってほしい」と、学校外の支援機関への紹介やつながりの重要性も指摘されました。
◯また、経済的困難だけでなく、「関係性の貧困」「体験の貧困」により社会性が育たない問題が深刻化しており、子ども期のコミュニケーション経験や手仕事・手作業の機会が激減しているとの指摘もありました。
◯ 「こどもも大人も安心して話せる相手がいない」「地域で大人同士が手を取り合ってこどもを育てる必要がある」といった意見からも、家庭や学校だけに頼らない地域ぐるみの支援体制の必要性が改めて浮き彫りとなりました。
◯お一人の委員からは、「こどもがここ(さいたまユースの堀崎拠点)に集まるきっかけは?」という質問があり、「学校の先生からの紹介というより、子ども間、親同士の口コミやSSWの紹介が多い」との回答がありました。
◯また、こども同士がつながれるような仕組みづくりへの期待も述べられました。
◯不登校の子どもたちについて、「無理はしないが、つながりをつくっていく姿勢が大切」と語られ、現場での粘り強い支援が必要であることが浮かび上がりました。
◯ある定時制高校の委員からは、「在籍46名のうち8割が不登校経験者」という現状が共有されました。制服や校則のない自由な環境であるにも関わらず、登校そのものが難しい生徒がいることから、「支援の手を校外にどう届けるか」という点が今後の大きな課題として提示されました。
◯ また、こども若者に関する貧困問題において、「親世代が地域活動に参加しない」「自治会や子ども会が機能しにくい」という現状も共有され、「子どもがふるさとをどこに感じて育っていけばいいのか」「地域にこそ安心できる居場所が必要」との発言もありました。
◯ これを受けて、地域ぐるみの支援に向けた展望、ローカル・コモンズの展望も語られました。
【ローカル・コモンズについて】
◯今回の協議会では、「地域社会が子どもや若者を支えるプラットフォーム」としての「ローカル・コモンズ」の概念が再確認されました。
◯学校や家庭だけでは担いきれない支援の空白を埋める仕組みとして、行政、地域団体、企業、住民が連携し、日常的な関わりの中で支援が行われる体制が求められています。
◯子どもたち自身が参加し、地域の一員として役割を担い、大人も共に楽しめるような活動が支援の担い手を広げる鍵となることも確認されました。